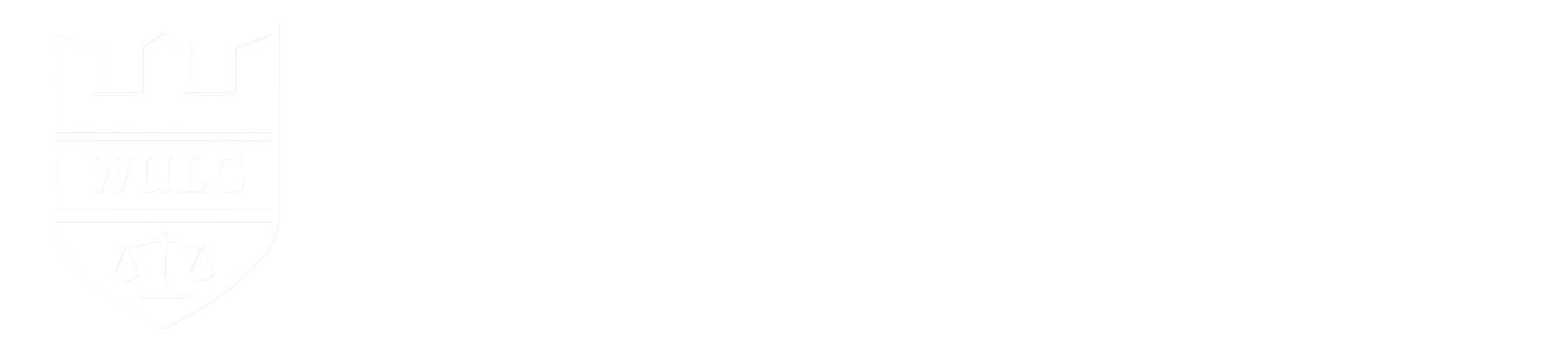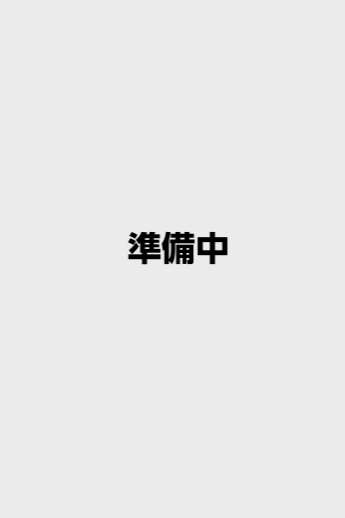
宮野 絢子 みやの あやこ
弁護士(東京弁護士会)
経歴等
2015年 早稲田大学法学部 卒業
2017年 早稲田大学大学院法務研究科 卒業
2018年 弁護士登録後、弁護士法人北千住パブリック法律事務所入所
2023年 当事務所入所
日弁連法務研究財団認証評価事業部嘱託
東京弁護士会 刑事弁護委員会
同 法曹養成センター
同 司法修習委員会
同 東京三弁護士会裁判員制度協議会
同 東京三弁護士会裁判員制度協議会
同 常議員(2023/4~2024/3)
日本弁護士連合会 代議員(2023/4~2024/3)
主な研究 / 実務テーマ
刑事(裁判員裁判対象事件含む)、家事(離婚・相続)、債務整理、労働、交通事故、その他一般民事
主要著書・論文等
※共著編著を含む